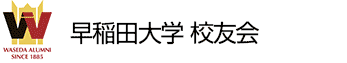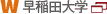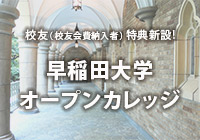- 知る
第13回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した降田天が短編ミステリーを書き下ろし
「ミステリー」が特集テーマの『早稲田学報12月号』では、校友ミステリー作家とのコラボレーションが実現! 『女王はかえらない』で第13回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した、降田天による短編ミステリーを掲載しています。今回はその短編をウェブでも特別に公開。大学にちなんだネタが文の中に織り交ぜられているところにも注目です!
『穴』 降田天
小学校一年生の時、家の庭に穴を掘って宝箱を埋めた。中身はなんだったか忘れたが、その行為自体にドキドキわくわくした気持ちは忘れられない。以来、いろんな場所に穴を掘っては、いろんなものを埋めた。タイムカプセルから、味噌汁のアサリの貝殻まで。
そんなぼくが大学で「穴掘り同好会」に出会ったのは、もはや運命としか言いようがない。会の目的は、ただ地面に穴を掘ること。道具は自らの手とシャベルのみ。なぜと問われれば、そこに地面があるからだ、と幹事長の木梨さんは新歓で熱く訴えていた。早稲田大学に砂の数ほどあるバカ同好会のひとつで、現在の会員は木梨さんとぼくのふたりだけだが、実は六十年の伝統を誇る名誉ある会なのだ。
「もっと思う存分、掘りたいよなあ」
長年多くの早大生をとりこにしてきた安くて大盛りの弁当を頰張りながら、木梨さんがため息をついた。頻繁に顔を出すOBの前田さんが、深くうなずく。入会して半年、ぼくはほとんど公園の砂場しか掘っていない。学生会館の部室にある古びた本棚には、六十年分の会員日誌が詰め込まれており、それによれば昔は山や砂浜をガンガン掘っていたという。しかし昨今、勝手に大きな穴を掘っていい場所は限られているし、この人数では活動の規模も資金も心もとない。
三人のため息が重なった時、ノックの音がした。現れたのは(大きな声では言えないがワセジョには珍しい)かわいい女子学生だった。
「ここ『穴掘り同好会』さんですよね。入会したいんですけど」
木梨さんが箸を落として立ち上がり、ぼくと前田さんも勢いよく顔を見合わせた。
「新歓の看板を見た時から興味は持ってたんですけど」
穴と雪のホニャララな看板を作ろうと強引に主張した木梨さんが、勝ち誇ったような目をぼくらに向ける。
女子学生は美園さんといって、資産家のお嬢さまだった。信州に山と別荘を持っているという。
「あの山ならいくらでも掘れますよ」
思いがけない女神の言葉にぼくたちは飛びついた。その週末にはレンタカーにシャベルを積んで高速道路を飛ばしていた。仕事が土日休みでない前田さんは、わざわざ有給をとっての参加だ。出発前には全員で戸山キャンパス向かいの穴八幡に立ち寄り、合宿の成功を祈願した。そのくらいぼくたちは飢えていたのだ。
別荘はこぢんまりとして、人里離れた山の中にぽつんとあった。中も外も掃除が行き届き、電気や水道もすぐに使える状態になっていた。ぼくらは荷物を置き、買ってきた食材をとりあえず冷蔵庫に押し込むと、さっそく森へ分け入った。道などないほったらかしの山で、十五分も歩くと四方の視界は木に閉ざされ、ふり返っても別荘は見えない。ぼくたちはほとんど無言で体を動かした。美園さんも手つきは頼りないが、軍手で汗を拭いながら熱心に掘り続け、暗くなってきても「もう少し」と粘った。
同じ穴を掘り、同じ釜の飯を食う。みんなで作ったカレーを食べている最中に、美園さんがいいことを思いついたと目を輝かせた。
「四人で来た記念に、四つの穴を掘ることにしませんか」
「おれはどっちかというと、ひとつの穴を深く追求したい派だな」
「じゃあ深い穴を四つ掘りましょうよ。わたし、まだまだやめたくないんです。うちの別荘は好きなだけ使ってくれていいですから」
四つ掘ることに反対した木梨さんも、それならと了承した。ぼくにも異存はない。少しくらい講義を休んでも単位は問題ないはずだし、この喜びには代えられない。期間は一週間ということになった。社会人の前田さんはさすがに日曜の夜に東京へ帰ったが、穴の完成には立ち会いたいから連絡してくれとしつこく念を押した。
一週間後、穴はほぼ完成した。深さ三メートルのものが四つ。型で抜いたようにそろい、やすりをかけたように滑らかだ。うちひとつだけは、こちらへ向かっている前田さんが最後にひと掻きできる状態で残してある。穴のふちに盛り上がった土を、ぼくはいとしくさえ感じた。木梨さんは感に堪えないという様子で穴の底を見下ろしている。
その木梨さんが、いきなり頭から穴に転げ落ちた。美園さんが後ろから蹴落としたのだ。目を見開いたぼくに、美園さんはナイフを突きつけた。
「自分から飛び込んだほうが痛くないよ。穴を掘ってくれたお礼。わたしひとりじゃ、ひとつだって無理だったもの」
穴の底でうめきながら身を起こした木梨さんが壁に手を当てるが、地表には届かず、壁はほとんど垂直で手足をかけられるでこぼこもない。自力で這い上がるのは不可能だ。
「なんでこんなこと……」
ぼくはうろたえおびえた。そう美園さんには見えただろう。彼女が優位を確信した隙をつき、ぼくはジーンズのポケットからスタンガンを取り出して腹にくらわせた。あっけなく気絶した美園さんを穴のふちまで引きずり、なるべく壁面を滑っていくように脚の方から落とす。
前田さんに電話をかけるとコール音も鳴らないうちに出た。
「やっぱり例のパターンでしたよ。穴掘り同好会に墓穴を掘らせようって、みんな考えるんですね」
部室にある六十年分の会員日誌で、何度か目にした事例だった。だから美園さんが入会したいとやって来たときから、ぼくと前田さんは疑っていた。こんな時期に? かわいい女の子が(これは偏見か)? いきなり山と別荘があるからどうぞ? そしてこちらへ来てみると、別荘は掃除が行き届き、すぐに使える状態になっていた。まるでつい最近まで使われていたように。
「今、別荘の地下室で男子学生の遺体を発見した。美園の恋人で、別荘の所有者の息子だ。遊び人だったから、親も友達もしばらく姿が見えなくても気にしてなかったらしい。ふたりでここへ遊びにきてトラブルになり、美園が彼を殺害したんだろう。おれたちに彼氏の墓を掘らせた上で口封じってわけだ」
警視庁にお勤めの前田さんは、慣れっこの口調だ。すぐに大勢の警察官とともにここへやってくるだろう。
「ひとつの死体を隠すために、三つ死体を増やすなんて」
「パニックになるとそういうもんさ。なんとかしようとして、かえって墓穴を掘る」
「壁の穴は壁で塞げ、ですね」
「そんな言葉、初めて聞いたぞ。文学部出身なのに。穴があったら入りたいよ」
状況をなんとなく理解したのか、木梨さんが穴の底で「人を呪わば穴ふたつだな」と重々しく言った。
前田さんが声をひそめる。
「不謹慎だが、おめでとう。念願かなって犯罪に遭遇できたじゃないか。その可能性に賭けて、うちに入会したんだもんな。ますます検察官になりたくなったろ」
はい、と答えながら、ぼくは穴の底の美園さんを見つめていた。白い頰にぱらぱらと土がかかっている。
埋めたい。体の奥から熱情が込み上げてくる。宝箱のように、タイムカプセルのように、アサリの貝殻のように。木梨さんも前田さんも知らないことだが、ぼくは本当は穴を掘りたいんじゃない、埋めたいんだ。だが実行したら犯罪者だ。美園さんと同じ穴のむじなになってしまう。ぼくは欲望に理性という名の土をかけた。
「穴って本当に奥が深いですよね」
ふるた・てん/萩野瑛(プロット担当)・鮎川颯(執筆担当)の二人からなる作家ユニット。2007年から鮎川はぎの名義で活動を開始。2014年に降田天名義で執筆した『女王はかえらない』(宝島社)で第13回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞。現在『彼女はもどらない』(宝島社)が発売中。
はぎの・えい/1981年茨城県生まれ。2004年第一文学部卒業。あゆかわ・そう/1982年香川県生まれ。2004年第一文学部卒業。
イラスト=こがしわ かおり(1991年人科)
毎号特集テーマを変えて、早稲田の今や社会で活躍する校友の姿を伝える、コミュニケーション誌『早稲田学報』。
校友会員の方は定価1,000円×6(隔月刊)=6,000円のところ、校友会費5,000円でご購読いただけます。
校友会員以外の方もご購読いただけます。また、1冊のみのご購入も可能です。