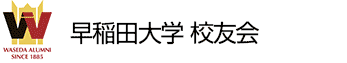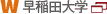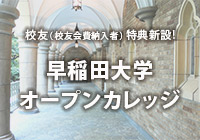- 知る
むらのない藍の中に、映し出される立体感

日本人の衣服を彩ってきた、美しき藍の色。相澤択哉さんは、入念な作業で藍を染め上げていく。
取材・文=牧浦 豊 撮影=布川航太
祭りに欠かせない紺半纏の藍染め
毎年5月に行われる浅草神社の三社祭。東京の初夏の行事を代表する伝統の祭りに欠かせないものの一つが、神輿の担ぎ手などが着る紺半纏だ。背に大きな紋などを鮮やかに染め抜いた深い藍色の半纏は、神輿を所有する町会などから色や模様にまつわる注文を受け、藍染職人たちの手でつくられている。その一人が、1906年創業の相澤染工場を五代目の兄と共に支えている相澤択哉さんだ。
「紺半纏づくりは、仕入れた木綿の生地を、用尺を計算して裁断し、身ごろや袖を取る位置を決めて『しるし』を付ける『つもり』から始まります。一反(約12メートル)の生地から、通常は半纏2着分の身ごろと袖が取れますが、生地はこの他に襟用のものが必要です」
しるしが付けられた生地は付着している油などが洗い落とされる(精練)。その後、紋や模様を切り抜いた型紙を、木枠に張った紗(薄い網状の織物)にニスや接着剤で固定し、それを「しるし」にしたがって生地に置いて、上からもち粉と糠でつくった糊を塗る(写真1)。型紙のある部分は生地に糊が付かないので、染めた際に色が付き、糊の付いた部分は白抜きになる。さらに、糊を塗った箇所にはおがくずをまぶし補強する(写真2)。染める際に、糊が剝がれ落ちたりしないようにするためだ。
糊を乾燥させたら、作業は「呉入れ」に移る(写真3)。大豆のつぶし汁である「呉(ご)」を生地に塗る作業で、大豆のタンパク質によって、藍がより染まりやすくなる。呉に、墨や樹皮を煮出した丹殻(たんがら)を入れると、より濃い藍色に染まる。薄手の生地などの場合は、濃くなり過ぎるのを防ぐため、墨や丹殻を入れないこともある。
呉を塗った生地を天日で干したら、ようやく藍染めだ。かつては藍草からとった天然藍が用いられ、阿波(徳島県)が天然藍の産地として有名だったが、糊を傷めずに濃く染めることができるとの理由で、化学的に合成した藍に切り替えているという。この藍を石灰や亜鉛の粉末などと一緒に甕に入れ、そこに生地をつけて染めていく(写真4)。最後に水で糊などを洗い流し、乾かして仕立て職人の下で仕立てられれば、紺半纏の完成だ。
紺半纏の納品まで、注文を受けてから約2カ月かかる。5月に行われる三社祭用の紺半纏は、3月から製作する必要がある。そして秋祭りが始まる9月まで、相澤染工場の忙しい日々は続く。

1. 糊を塗る工程。むらなく正確に糊を塗るには、経験が求められる
2. 糊にまぶすおがくず。きめの細かい特注品で、専門の業者から仕入れる

3. 呉入れ。ぴんと伸ばした生地に、手早く塗っていく
4. 藍染め。藍の濃淡が異なる甕が多数あり、必要に応じて使い分けている
藍染めの魅力を現代の暮らしに伝える
紺半纏や暖簾などの注文生産に携わる一方で、相澤さんは、オリジナルデザインの藍染めの布を使ったハンカチやストール、Tシャツ、ポーチや財布といった小物などを、「ものあい」というブランドで製作している。「ものあい」には、「物と藍、物と間、monoと藍」の三つの意味が込められていて、相澤さんは「伝統的な藍染めの技術を使って、暮らしになじむ自然な風合いの製品を手づくりしています」と話す。
「むらなく染めても、どこか立体的に見えるのが藍染めの良さ」と語る相澤さんは、長い歴史と文化の後継者として、また藍染めの新しい魅力の発信者として、多様な活動を続けている。

相澤染工場でつくられたものあいの「藍染ハンカチ」(写真左)と、紺半纏(写真右)
藍染職人 相澤択哉
あいざわ・たくや/1987年埼玉県生まれ。2010年社会科学部卒業後、株式会社日本触媒に入社。13年より自身のブランド「ものあい」の活動を開始。15年、日本触媒を退職し、相澤染工場に入社。
毎号特集テーマを変えて、早稲田の今や社会で活躍する校友の姿を伝える、コミュニケーション誌『早稲田学報』。
校友会員の方は定価1,000円×6(隔月刊)=6,000円のところ、校友会費5,000円でご購読いただけます。
校友会員以外の方もご購読いただけます。また、1冊のみのご購入も可能です。